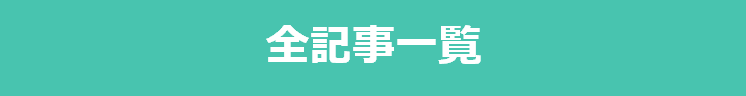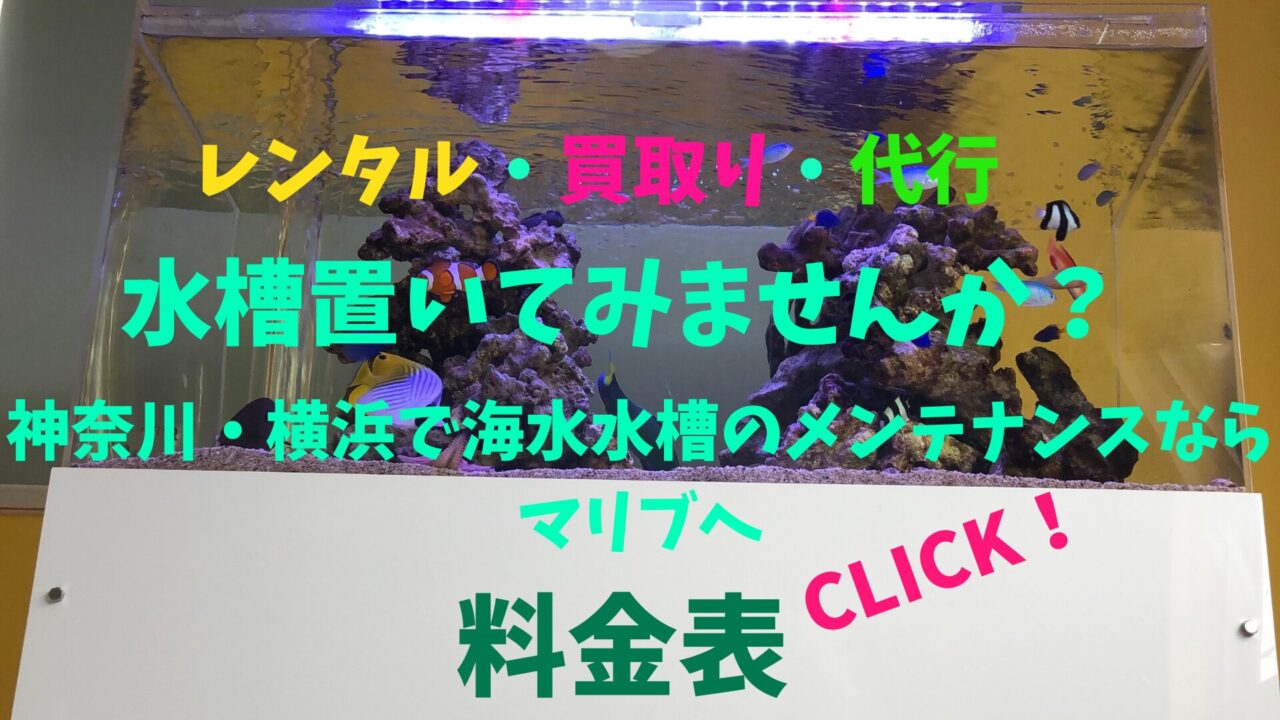こんにちは。神奈川・横浜の海水水槽専門レンタル・メンテナンスのマリブのウブカタです。
アユは、生まれた稚魚の時期に一度海へ行くとご存知でしたか?
これ、意外と驚かれます!それではどうぞ!
アユの稚魚は一度海へ行く
稚魚期に海へ行くアユ
川の下流で生まれた稚魚は、一旦、海へ出ます。
湾内でプランクトンを食べて冬を過ごし、春になると生まれた川へ上っていきます。
サケに比べると海にいる期間がわずかです。
川に上る頃は数センチの稚魚でしかなく、その後に中流・上流域で成長し秋に下流へ下って産卵します。
つまり、1年の大半を川で過ごし、一時期だけ海に下っているのです。
アユは川魚のイメージが強いですが、一度海へ行くというのも初めて知った方は驚きではないでしょうか。
川を上った幼魚は、次第にプランクトンや水生昆虫など動物性の餌から離れ、藻類(そうるい)を好んで食べるようになります。
やがて餌の確保のために縄張りを作るようになり、縄張り内に他の個体が入ってくると激しく争います。
この習性を利用したのがアユの友釣りです。
秋が来て産卵期を迎えると体色が黒くなります。
これは「さびアユ」と呼ばれます。
秋が深まると下流へ下り、産卵してそのライフサイクルを閉じます。
産卵後はほとんどのアユは死んでしまいます。
そのため、「1年魚」とか「年魚」と呼ばれます。
しかし、水温が高く餌の豊富な南日本などでは産卵後も生き延びる個体がいて、「フルセ」と呼ばれています。
水槽内で生殖させずに飼育すると2年以上も生きる例があります。
湖を海代わりにするアユもいる
琵琶湖のアユは他の河川のアユと同じ種類なのですが、成魚でも10㎝くらいにしかなりません。
そのため、「子アユ」とか「湖アユ」と呼ばれます。
普通のアユは海へ下り、大きさも20㎝~30㎝になりますが、湖アユは海へ下らずに、琵琶湖を海代わりにしています。
大きさの違いは餌などの量によるものと推測されています。
実際、湖アユの稚魚を他の河川に放し、一度海へ降下させると通常通りの大きさに育ちます。
回遊で有名なサケも川と海の両方行き来します。
一旦海へ出ますが、海で長く暮らし、産卵のためにだけ川へ戻ります。
こうしたサケ型の回遊スタイルを遡河回遊(そかかいゆう)といいます。
ウナギは逆に海へ下り産卵するため、降河回遊 (こうかいかいゆう)といいます。
海で孵化したウナギの稚魚は長い航海をして、故郷の川へ戻って暮らすのです。
これに対し、アユのような稚魚期の成長のためだけに海へ出て、幼魚のうちにまた川に戻る生活を両側回遊 (りょうそくかいゆう)といいます。
★関連記事★
【ワカサギ飼育】ワカサギは淡水魚?海水魚?フッフッフッ・・・実は両方イケる魚なんだぜ!
※マリブでは水槽おすすめ商品を皆様にわかりやすくご案内しています!
★おすすめ商品★
おすすめ商品カテゴリー(クリックすると一覧が出てきます)
水槽掃除グッズ・水質測定試薬全種類・クーラー・ヒーター・サーモスタッド・外部式フィルター・LEDライト 水槽台・照明タイマー・フードタイマー・水槽用マット・エアーポンプ・エアチューブ・エアストーン・水流ポンプ・水中ポンプ・カルキ抜き・ウールマット・比重計・水温計・人工海水・ろ材・底砂・phモニター・殺菌灯・人工餌・冷凍餌・スポイト・ピンセット・網・バケツ・隔離ケースなどなどたくさんのアクアリウムのおすすめ商品を掲載しています!
まとめ
アユは稚魚期に海へ一度行ってすぐに川へ戻ってくる!
新着情報
最新記事 by マリブ(海水水槽専門メンテナンス) (全て見る)
- 【魚のサイズの測り方は手で一発でわかる編】水槽レンタルで変わった生態の魚が見たい!完全解説! - 2025-12-31
- 【水槽付近で殺虫剤を使用する時の3つの対策方法編】水槽レンタルで変わった生態の魚が見たい!完全解説! - 2025-12-30
- 【海水水槽には”淡水水槽で使用していた底砂”は使用してはいけない理由編】水槽レンタルで変わった生態の魚が見たい!完全解説! - 2025-12-29