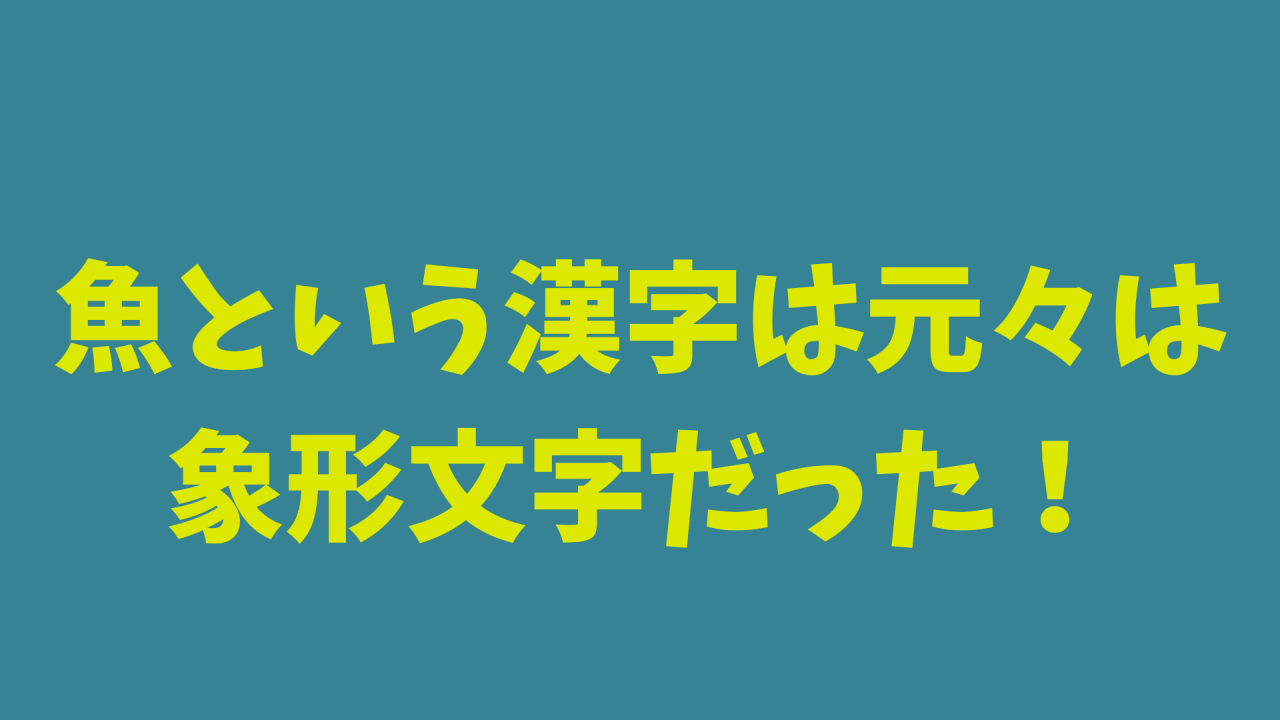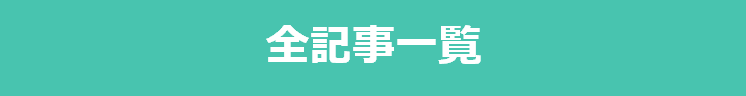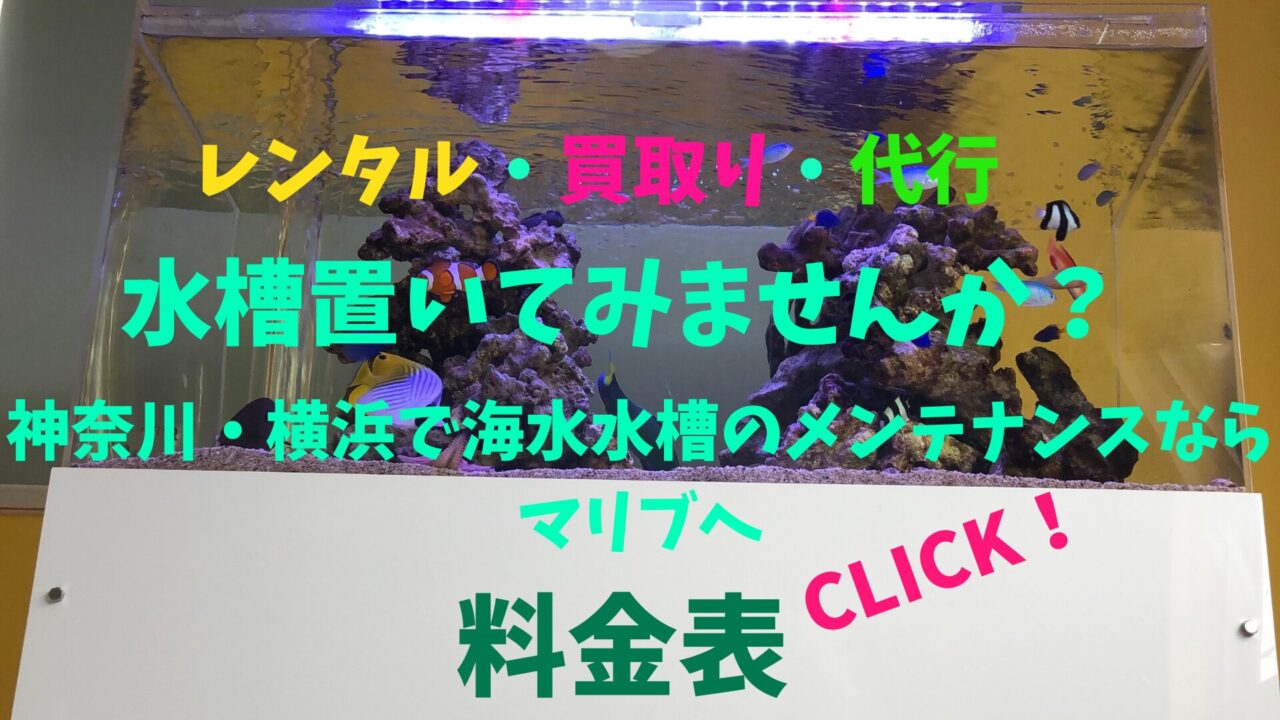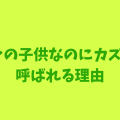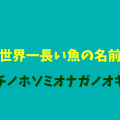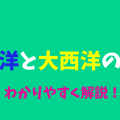こんにちは。神奈川・横浜の海水水槽専門レンタル・メンテナンスのマリブのウブカタです。
『さかな』の語源って何???
【結論】
酒のつまみの肴(さかな)は、肉も魚も一緒のくくりで『さかな』と呼ばれていました。
しかし、肉よりも魚の方が手に入る機会が多かったために、魚のことだけを魚と呼ぶようになったのでした。
そんな『さかな』と呼ばれた語源を楽しく学びましょう!
『さかな』と名付けられた語源

『さかな』の語源は何?
江戸時代から、【酒菜(さかな)】と呼び、お酒を飲む時に添えて食べるものの意味です。
その酒菜(さかな)のうち、魚や肉のような動物性食品を【真菜(まな)】と呼び、野菜のような植物性食品を【疏菜(そな)】と呼んでいました。
しかし、酒のサカナ(肴)としては、昔は肉より魚が多かったことから、魚のことだけを
【さかな】と呼ぶようになったとのことです。
ちなみにその真菜(まな)を料理する板だから、真菜板と呼ばれるようになりました。
まとめると・・・
酒のつまみの肴(さかな)は、肉も魚も一緒のくくりで『さかな』と呼ばれていました。
しかし、肉よりも魚の方が手に入る機会が多かったために、魚のことだけを魚と呼ぶようになったのでした。
元は象形文字だった!

『魚』という字は、魚の頭・胴(どう)・ひれを表した象形文字からできたというのが有力です。
また魚を『ウオ』と訓読みします。
これは江戸時代に貝原益軒(かいはらえきけん)という学者が【鱗ありて泳ぐゆえ、鱗のウと泳ぐのオをとりてウオといふ】と記したそうです。
簡単に言うと、造形語ってことですね。
海外では『fish(フィッシュ)』だが、呼び方はたくさんある!
海外(英語)では魚類は一般的に『fish(フィッシュ)』と呼ばれます。
それ以外にも、
●シェルフィッッシュ(Shell fish):エビ・カニ・貝などの殻のあるもの
●カトルフィッッシュ(Cuttle fish):コウイカ類のように甲のあるの
●スターフィッッシュ(Star fish):ヒトデ類のように星型のもの
●ジェリーフィッッシュ(Jelly fish):クラゲのようなジェリー状のもの
意外と細かくあるんですね~。
★語源・由来関連記事★
【魚の名前(和名)が変更】2007年に名前が変更された32種の海水魚たち!
天皇陛下が付けた海水魚たちの名前!ウソ!あの超有名な”アケボノハゼ”もそうだった!
※マリブでは水槽おすすめ商品を皆様にわかりやすくご案内しています!
★おすすめ商品★
おすすめ商品カテゴリー(クリックすると一覧が出てきます)
水槽掃除グッズ・水質測定試薬全種類・クーラー・ヒーター・サーモスタッド・外部式フィルター・LEDライト 水槽台・照明タイマー・フードタイマー・水槽用マット・エアーポンプ・エアチューブ・エアストーン・水流ポンプ・水中ポンプ・カルキ抜き・ウールマット・比重計・水温計・人工海水・ろ材・底砂・phモニター・殺菌灯・人工餌・冷凍餌・スポイト・ピンセット・網・バケツ・隔離ケースなどなどたくさんのアクアリウムのおすすめ商品を掲載しています!
まとめ
『さかな』の語源は肉も魚も同じくくりだった!
しかし、魚の方が多く食卓に並んでいた為、肉・魚のうち、『魚』だけを取り、『魚』と呼んだのがはじまり!
新着情報
最新記事 by マリブ(海水水槽専門メンテナンス) (全て見る)
- 【魚のサイズの測り方は手で一発でわかる編】水槽レンタルで変わった生態の魚が見たい!完全解説! - 2025-12-31
- 【水槽付近で殺虫剤を使用する時の3つの対策方法編】水槽レンタルで変わった生態の魚が見たい!完全解説! - 2025-12-30
- 【海水水槽には”淡水水槽で使用していた底砂”は使用してはいけない理由編】水槽レンタルで変わった生態の魚が見たい!完全解説! - 2025-12-29