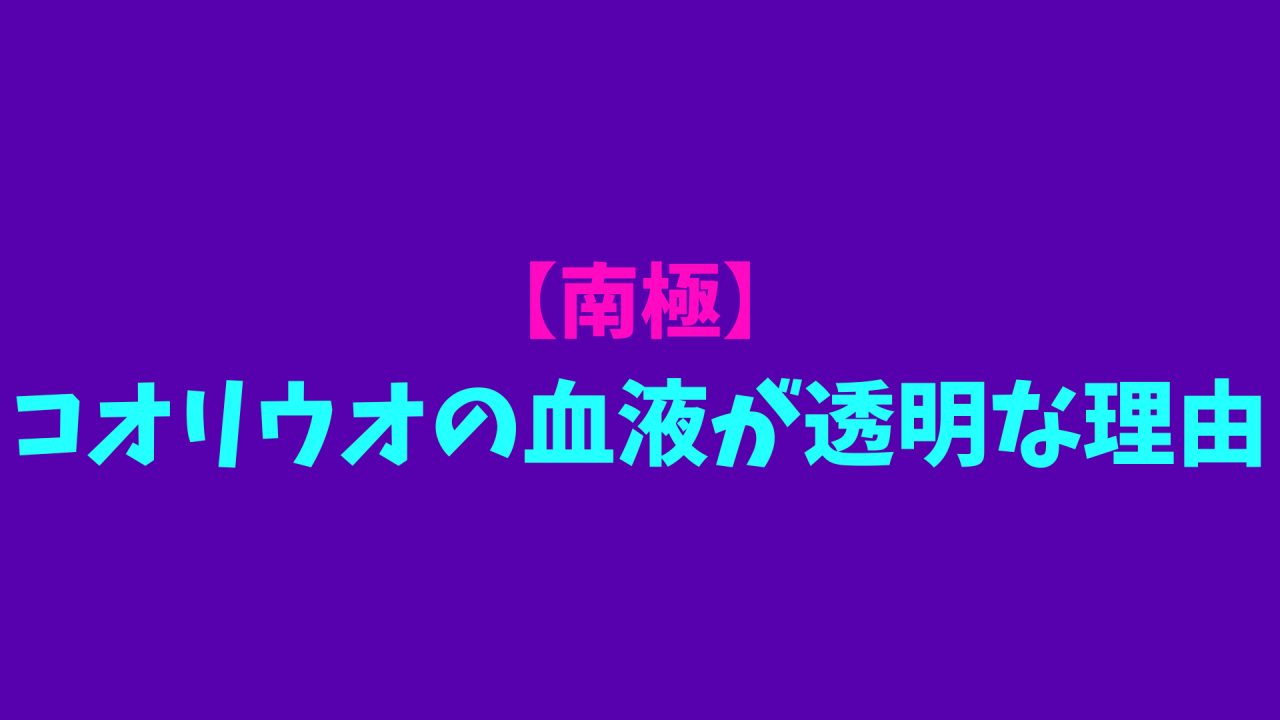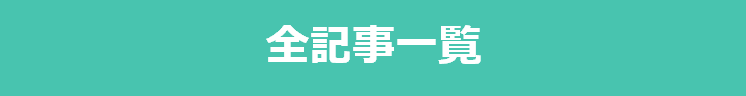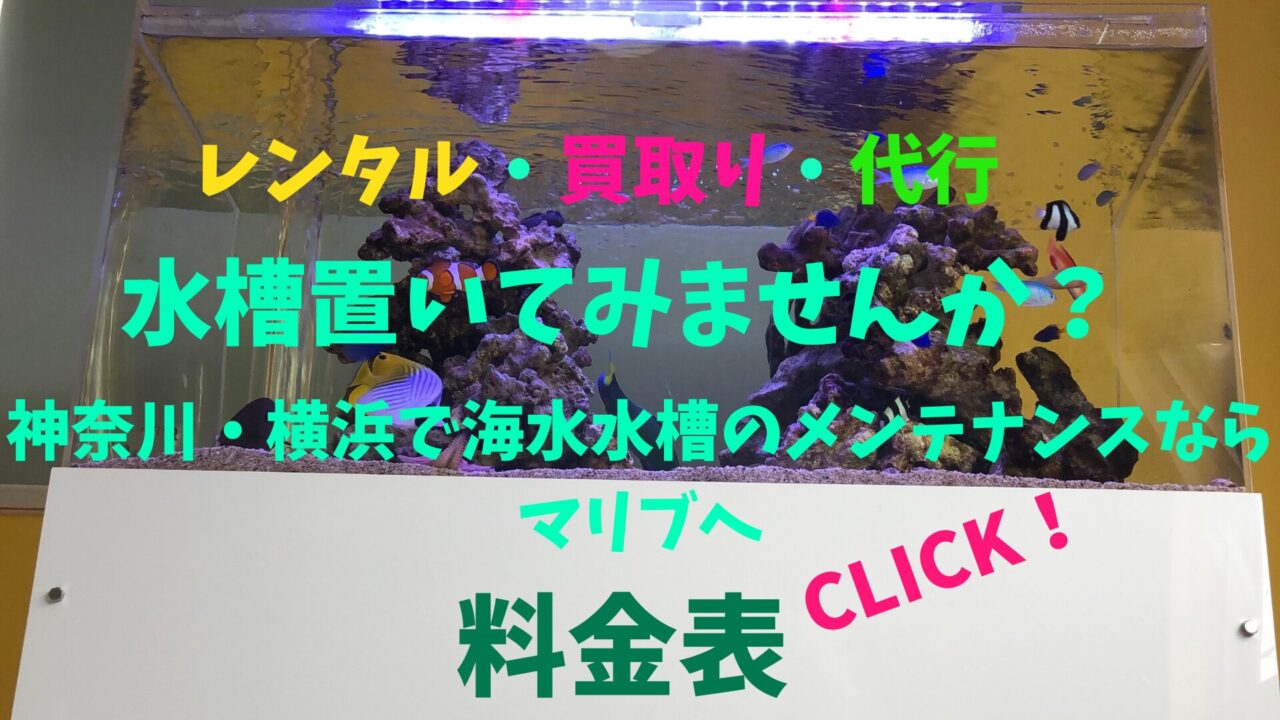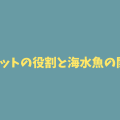こんにちは。神奈川・横浜の海水水槽専門レンタル・メンテナンスのマリブのウブカタです。
僕たち人間の血液は赤です。
そして、ほとんどの魚の血液も赤です。
何故、血液が赤いかと言うと、血液中にヘモグロビンという赤い色素が含まれているからです。
しかし!
透明の血液をする海水魚が世の中にはいるのです!
その海水魚は・・・コオリウオ
冷たい南極海に棲む海水魚です。見るからに冷たそうな魚ですね(笑)
ちなみに何故、南極の冷たい海でも生きられるかは、北極・南極の水温は平均-2℃だよ!なんで魚は凍らないの!?をご覧ください!
ヘモグロビンは血液中の酸素と結合して輸送するという呼吸に過程においてなくてはならない重要な役割を持ちます。
えっ!それで大丈夫なの?呼吸はできるの?それをご案内します!
画像は著作権に引っ掛かってしまうので”コオリウオ”でググれば出てきます。
コオリウオの血液が透明の理由
コオリウオとは?
南極海を中心に生息するノトテニア亜目(Notothenioidei)に属する科。
ほとんどの種は赤血球をもたない。
現在コオリウオ科には16種が確認されている。
ポイントは体内に入った血液中の酸素が”溶けたまま”の状態というコト
コオリウオの血液にはヘモグロビンがありません。
海水からエラを通して”体内に入った酸素は血液中に溶けたまま”の状態で運ばれることになります。
水に溶けている状態の物質は、気体も含めて濃度の高い所から低い所へ移動する性質があります。
このとき濃度差が大きいほど、物質の移動する力も大きくなります。
また、気体は温度が低いほど、水に溶ける量も多くなります。
極寒の南極海では海水中に溶ける酸素の濃度が高くなり、コオリウオの血液と海水との間の酸素の濃度差も大きくなっています。
さらに、コオリウオの血液の粘液も他の魚に比べて非常に低く保たれ、血液中を酸素が移動しやすくなっているのです。
このように、コオリウオはヘモグロビンが無くても、酸素が血液中に容易に溶け込み、血液中を移動しやすくなっているのです。
それでも酸素が足りない!そんな時は・・・
とは言っても、運動時にはとてもウロコから溶け込む酸素だけでは足りません。
コオリウオのヒレは体に対して非常に大きく発達しており、その体表面に毛細血管が多数に分布されてます。
これらの毛細血管がウロコの働きを補っているのです。
ウロコや体表面から取り込まれる酸素の量は、呼吸量全体の40%にも達すると言われています。
さらに運動時や海水中の酸素量が低下した時には、血液の体積を増やして、体内に溶け込む酸素の量を維持する仕組みもあるのです。
★関連記事★
【わかりやすい】南極の氷と北極の氷の違い!もし溶けたら・・・
※マリブでは水槽おすすめ商品を皆様にわかりやすくご案内しています!
★おすすめ商品★
おすすめ商品カテゴリー(クリックすると一覧が出てきます)
水槽掃除グッズ・水質測定試薬全種類・クーラー・ヒーター・サーモスタッド・外部式フィルター・LEDライト 水槽台・照明タイマー・フードタイマー・水槽用マット・エアーポンプ・エアチューブ・エアストーン・水流ポンプ・水中ポンプ・カルキ抜き・ウールマット・比重計・水温計・人工海水・ろ材・底砂・phモニター・殺菌灯・人工餌・冷凍餌・スポイト・ピンセット・網・バケツ・隔離ケースなどなどたくさんのアクアリウムのおすすめ商品を掲載しています!
まとめ
コオリウオはウロコや体表面で非常に効率よく酸素を取り込み、低い酸素濃度の環境にもよく耐える機能が備わっているのです。
今回の記事は難しすぎてあまり見てくれないかもしれません・・・おもしろいんですけどね・・・笑
最後まで見てくれた貴方に捧げます。
新着情報
最新記事 by マリブ(海水水槽専門メンテナンス) (全て見る)
- 【魚のサイズの測り方は手で一発でわかる編】水槽レンタルで変わった生態の魚が見たい!完全解説! - 2025-12-31
- 【水槽付近で殺虫剤を使用する時の3つの対策方法編】水槽レンタルで変わった生態の魚が見たい!完全解説! - 2025-12-30
- 【海水水槽には”淡水水槽で使用していた底砂”は使用してはいけない理由編】水槽レンタルで変わった生態の魚が見たい!完全解説! - 2025-12-29