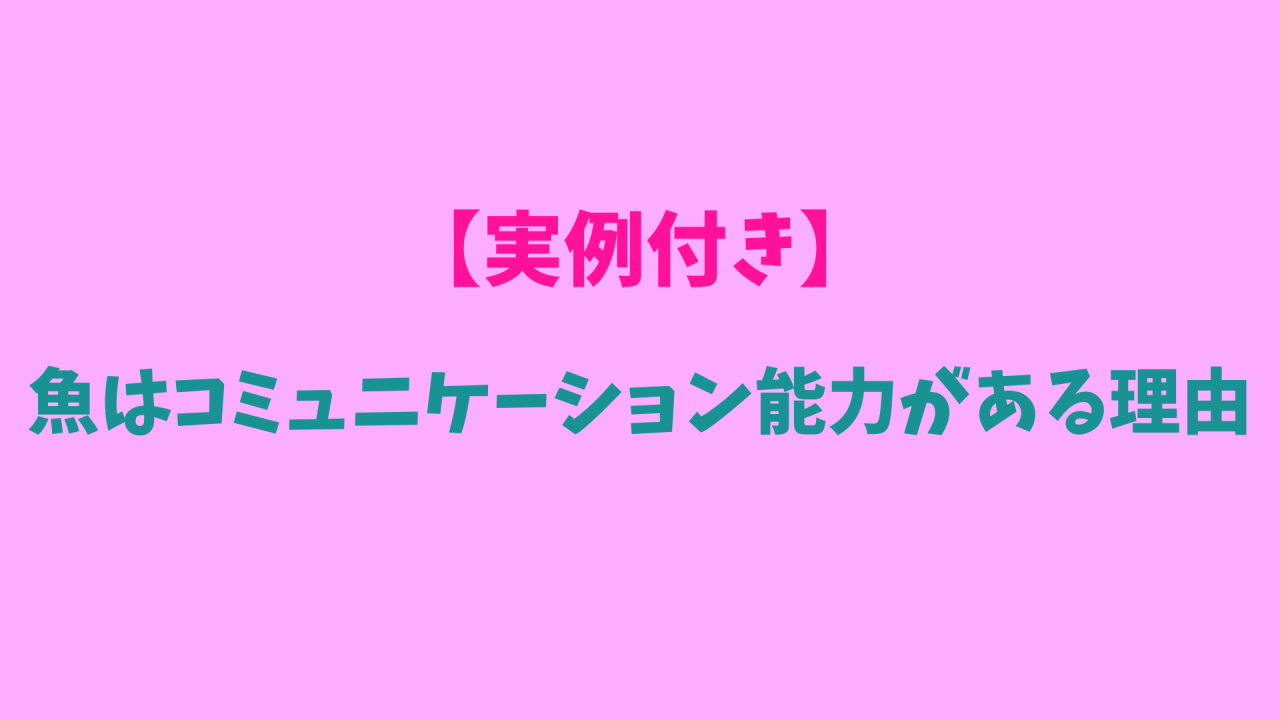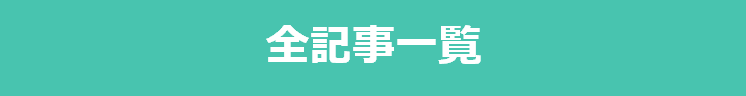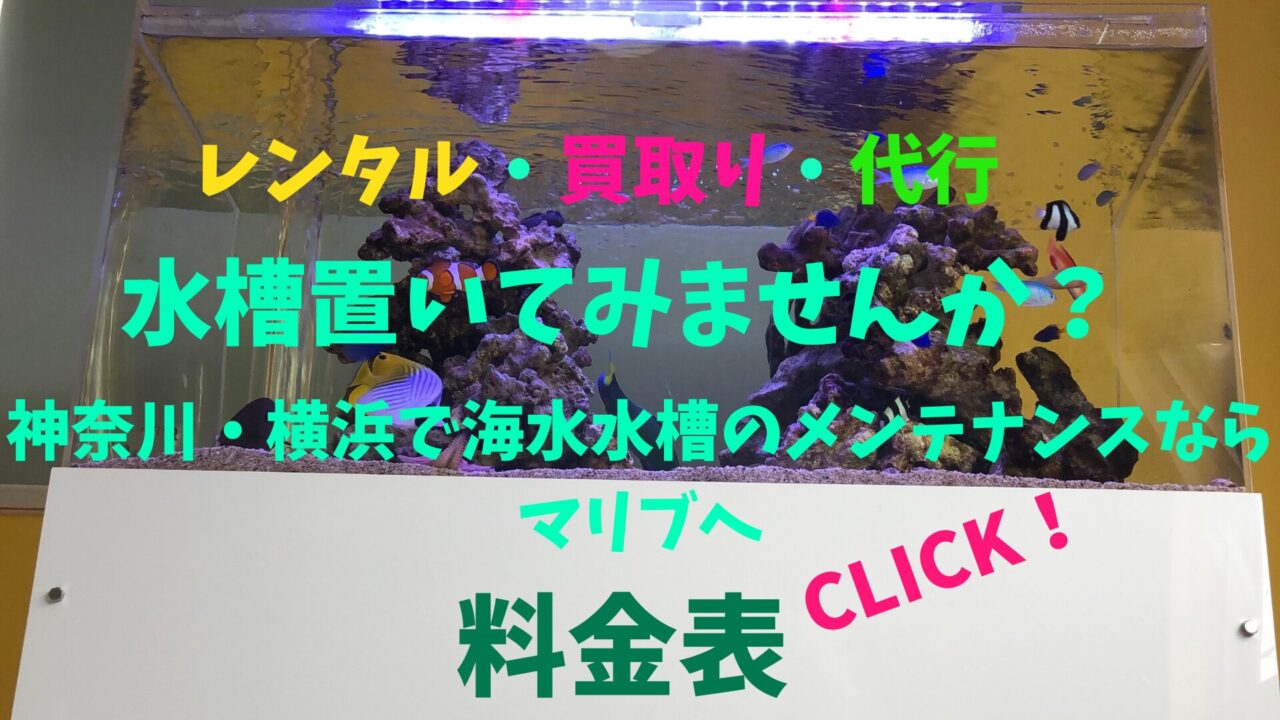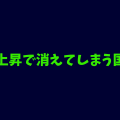こんにちは。神奈川・横浜の海水水槽専門レンタル・メンテナンスのマリブのウブカタです。
魚にはコミュニケーション能力がある理由!
未だに科学的に解明されてはいませんが、実例付きで皆様にご案内します!
魚の新たな発見にあなたは今日気付きます!どうぞ!
★関連記事★
目次
発光器でコミュニケーションするヒカリキンメダイ

なんで光で会話をしていると言われてるか?
まずすみません。画像はググってくださいませ。
ヒカリキンメダイは、群れで暮らしています。
暗い場所でお互いに発光器を点滅させて、コミュニケーションを図っていると考えられています。
発光の正体はバクテリア
ヒカリキンメダイは、目の下に暗闇で光る発光器をもちます。
発光器のなかに発光バクテリアを取り込むことで発光しています。
発光器は楕円形(だえんけい)で普段は、黄白色の光る面を外側に向けて付いています。
発光器そのものを回転させ、裏側の黒色の面を外側に出すことで光を細かく点滅させることができます。
この発光器でコミュニケーションを取っていると考えられています。
実際に魚がコミュニケーションを取り合っている例

カワハギは縞が濃い個体が強く、縞が薄い個体が弱い
カワハギは水槽内で如実に力関係が現れます。
カワハギの特徴として、エサの時に1番強い個体が先に食べたのを確認してから弱い個体が食べます。
つまり、力関係ができるということは魚同士のコミュニケーションが成立しているからこその結果であると裏付けできます。
★カワハギ関連記事★
カワハギは”縞模様の濃さ”で力関係を表している!ボスがすぐわかる!
鳴く魚もいる!
魚が音を発する場合の多くは、【浮き袋の振動】によるものです。
浮き袋にくっついてる筋肉が収縮することによって、浮き袋がの壁に振動を与えて音を出すわけです。
また、歯や骨などの硬い部分をこすり合わせて音を出す魚もいます。
『フグ』は上下の歯を噛み合わせて【ギギギッやグゥ~グゥ~】と鳴きます。
鳴く理由の有力候補
①泳いだり、呼吸したり、エサを食べるときにともなって発する
②互いの存在を知らせ合う合図のため
③相手を警戒したり、威嚇するため
これもコミュニケーションがあってこその反応です。
鳴く魚で有名なのは、ホウボウ・シログチ・フグです。
★鳴く関連記事★
★ミドリフグ関連記事★
薄暗い水中や暗闇の中でコミュニケーションを取るために音を出す
魚は楽器を使うことなく、ハ調のドの音やソの音が分かります。
魚は互いに音を出して、薄暗い水中や暗闇の中で通信し合うには、音を出すのが一番便利で効率的だからです。
水中では空中の3倍も音が早く伝わることと、音が消えにくいなどの理由から用いられてるといわれています。
音を出す理由
●エサを食べるときの捕食音
●相手を脅かす威嚇音
●敵の接近や危険を感じたときの警戒音
●異性が呼び合う生殖音
●泳ぐときに自然に発する遊泳音
体色変化
他の魚に追い回されてたり、プレッシャーを感じると警戒色を出す海水魚も多いです。
ヒフキアイゴなんかはモロに色が変わります。
これもコミュニケーションがあってこその反応です。
★体色関連記事★
★ヒフキアイゴ飼育記事★
【プロ解説】ヒフキアイゴの飼育方法!おとなしくて力持ち!コケも食べてくれる!
★関連記事★
※マリブでは水槽おすすめ商品を皆様にわかりやすくご案内しています!
★おすすめ商品★
おすすめ商品カテゴリー(クリックすると一覧が出てきます)
水槽掃除グッズ・水質測定試薬全種類・クーラー・ヒーター・サーモスタッド・外部式フィルター・LEDライト 水槽台・照明タイマー・フードタイマー・水槽用マット・エアーポンプ・エアチューブ・エアストーン・水流ポンプ・水中ポンプ・カルキ抜き・ウールマット・比重計・水温計・人工海水・ろ材・底砂・phモニター・殺菌灯・人工餌・冷凍餌・スポイト・ピンセット・網・バケツ・隔離ケースなどなどたくさんのアクアリウムのおすすめ商品を掲載しています!
まとめ
ヒカリキンメダイが光る理由は、仲間とのコミュニケーションを取っているのではないかと言われている!
その他にもコミュニケーションを取り合っている例もあります!
新着情報
最新記事 by マリブ(海水水槽専門メンテナンス) (全て見る)
- 【魚のサイズの測り方は手で一発でわかる編】水槽レンタルで変わった生態の魚が見たい!完全解説! - 2025-12-31
- 【水槽付近で殺虫剤を使用する時の3つの対策方法編】水槽レンタルで変わった生態の魚が見たい!完全解説! - 2025-12-30
- 【海水水槽には”淡水水槽で使用していた底砂”は使用してはいけない理由編】水槽レンタルで変わった生態の魚が見たい!完全解説! - 2025-12-29